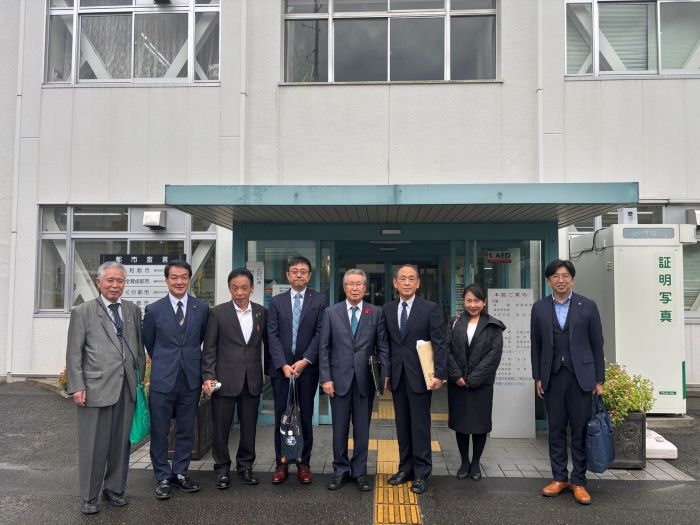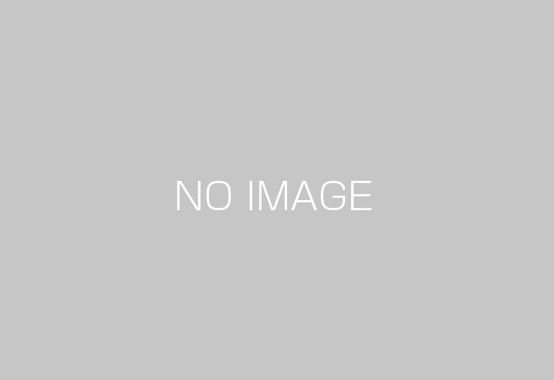令和7年10月22日から24日にかけて、熱海市議会総務福祉教育委員会にて、大阪府四条畷市と兵庫県高砂市へ行政調査に行きました。
まず、この公式ホームページでは、part1とpart2に分けて行政調査の詳細を報告いたします。
まずは、初日の大阪府四条畷市『書かない窓口』です。
 行政視察報告書 【総務福祉教育委員会委員 橋本一実】
行政視察報告書 【総務福祉教育委員会委員 橋本一実】
視察先:大阪府四條畷市
視察調査テーマ:行政DX「書かない窓口」導入背景と概要について
日時:令和7年10月22日 午後2時~
場所:四条畷市役所 委員会室
1.四條畷市の概要
大阪府北東部に位置する四條畷市は、奈良県との県境に接し、その大部分が生駒山地の麓に広がる自然豊かな都市である。 南北朝時代の「四條畷の戦い」(1348年)の古戦場として知られ、楠木正成の子・正行(まさつら)が奮戦した地として歴史的にも著名である。
戦後は大阪市のベッドタウンとして住宅開発が進み、人口が急増。1970年(昭和45年)7月1日に市制を施行し、大阪府下で32番目の市として誕生した。 豊かな自然と歴史遺産を背景に、都市近郊型のまちとして発展を続けている。
2.人口の推移
1960年代の宅地開発に伴い人口が急増。1960年から1965年にかけての増加率は府下最高の79.6%を記録した。 1975年には52,368人で一旦ピークを迎えたが、関西文化学術研究都市の指定を受けた田原地区の開発により再び増加に転じ、2003年には57,000人を突破。 2010年(平成22年)の57,554人をピークに一時横ばい傾向となったものの、近年は再開発や新興住宅地整備により再び増加傾向にある。 令和2年国勢調査時点で約55,000人、住民基本台帳による令和6年度の人口は約53,700人。
 3.市議会の概要
3.市議会の概要
議員定数 平成27年9月の選挙から16名から12名に変更
平成27年3月 議会基本条例制定 これ以後議会基本条例に基づいた取り組みを実施
平成29年5月から通年会期制導入
平成30年度から本会議の録画配信、令和元年6月定例議会からライブ配信を始めている
令和4年12月定例議会からライブ映像における字幕配信を開始
令和7年1月の委員会から録画配信、ライブ配信を開始した。
4.行政DXの推進方針
四條畷市では、「持続可能な行政運営」を目指し、令和5年度にDX推進計画を策定。 市民サービスの利便性向上と業務効率化の両立を目的として、積極的にデジタル技術を導入している。
 5.「書かない窓口」とは
5.「書かない窓口」とは
「書かない窓口」は、マイナンバーカード等の本人確認書類から氏名・住所などの情報を自動で読み取り、 申請書に自動印字する仕組みである。
これにより、住民は手書きでの記入が不要となり、
- 手続き時間の短縮
- 記入ミスの防止
- 職員の事務負担軽減 といった効果が期待されている。
また、窓口での待ち時間が減少し、利用者満足度の向上にもつながっている。
6.導入経緯
令和3年1月開始のマイナポイント事業を契機に関連業務が急増し、市民課窓口の負担が著しく増大した。これを背景に、市民の利便性を高めるとともに、職員の負担軽減を目的として検討が始まり、
庁内での調整・業務フロー見直しを経て令和5年11月より本格運用を開始した。
導入にあたっては、複数課にまたがる業務整理や個人情報管理の調整など、庁内調整に相当の労力を要したが、 「まずはできるところから始める」姿勢で小規模導入を行い、段階的に拡大している。
 7. 導入効果と課題
7. 導入効果と課題
<主なメリット>
- 住民記入負担軽減
- 時間の大幅削減 窓口滞在時間の短縮
- 職員による入力ミス・再確認作業の削減
- 高齢者・外国人にもわかりやすい手続き画面
<デメリット・課題>
- システム導入・改修コストの発生
- 一部の非対応証明書(転出証明・戸籍関連・パスポート等一部対象外)
- イレギュラー案件は、紙申請での対応
- 窓口職員の人員体制が依然ひっ迫している導入効果十分波及しにくい
- マイナンバーカードを利用しない市民への説明負担
- 書かない窓口導入後も申請書は印刷する 直接的な紙削減には至っていない
- 窓口端末の操作トラブル時のバックアップ体制の必要性
 8.今後の展開
8.今後の展開
- 対象続きの拡大を順次検討、また入力の簡素化・簡略化を図る
- オンライン申請との一体運用化
- 窓口案内のデジタルサイネージ化 などを計画している。
最終的には、「市民がどこでも・いつでも行政手続を完結できる環境」を目指しており、 デジタル技術を行政運営の基盤として位置付けている。
9.他自治体への示唆
「書かない窓口」は、単なるシステム導入ではなく、 職員業務の見直しや市民目線での設計が成功の鍵であることが明らかとなった。
特に四條畷市の事例は、
- 小規模自治体でも実現可能な現実的DXモデル
- 段階的導入によるリスク低減
- 職員意識改革と市民理解の両立 という点で他自治体の参考となる。
10.所感
まず、今回の視察にあたり、四條畷市の市職員の皆様、ならびに四條畷市議会の皆様には、快く行政調査を受け入れていただき、心より感謝申し上げます。
また、当日はご多忙の中、藤本美佐子議長様より歓迎のご挨拶を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。
「書かない窓口」導入から約1年が経過し、来庁者の本人確認や聞き取り内容をもとに、職員とともにタブレットを操作してシステムに入力し、申請書を自動作成する仕組みが確立されていた。
これは、手続きの効率化を図る上で最大の効果を発揮しており、特に引っ越し手続きでは、事前の設問に回答することで関係課の必要手続きを自動判定し、案内表を作成する「迷わない窓口」の実現につながっている。
さらに、証明書発行専用機の導入により、マイナンバーカードを持参すれば申請書を作成することなく住民票の写し等を交付できる「待たない窓口」としてのサービス提供も行われていた。
導入に際しては、窓口職員の業務フロー変更に伴う説明・操作研修、各担当課との調整、帳票や設問内容の精査、運用開始後の仕様調整など、多方面での労力を要したとのことであった。
効果の一例として、夫婦2名・小学生2名の世帯が転入手続きを行う場合、導入前は68回に及んでいた記入項目が、導入後はわずか9回にまで削減されたと伺った。
一方で、導入経費やランニングコストの確保、費用対効果の明確化、そして窓口とオンラインの双方で申請を受け付けることによる管理の煩雑化など、今後の課題も示されていた。
また、電子サインによるPDF管理には検索性などの利点がある一方、現行の職員体制では運用面での課題が残るとのことであった。
今回の視察を通じ、四條畷市の「書かない窓口」は、単なるデジタル化ではなく、市民の利便性向上と職員の業務効率化を両立させる、実効性の高い取組であると実感した。
特に、「まずはできるところから始める」という段階的導入の姿勢や、庁内連携・職員研修を重視した体制づくりは、小規模自治体でも実践可能な現実的DXモデルとして大いに参考となった。
また、「書かない」だけでなく、「迷わない」「待たない」窓口を目指す仕組みづくりは、市民に寄り添った行政サービスの理想形であると感じた。
今後、本市においても、こうした先進的な取組を参考に、行政手続のデジタル化を単なる効率化にとどめず、誰もが安心して利用できる“やさしいDX”として推進していく必要があると考える。
【導入経費】
企画料418万円
ハード購入費端末等 1000万円
月コスト保守料 66000円 利用料407000円
市民利用端末6台 証明書交付機3台